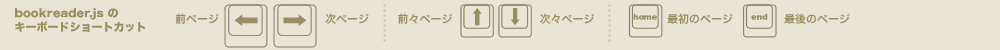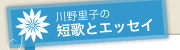ホーム
初出「現代短歌雁」98・9
(一部書き換え 『未知の言葉であるために』所収)
白秋が〈桐の花〉に記した短歌という定型のイメージ、「短歌は一箇の小さい緑の古宝玉である」は、この短詩型のエッセンスを語るたびに引用され愛されてきた。この言葉は次のように続く。「短歌は一箇の小さい緑の古宝玉である。古い悲哀時代のセンチメントの精(エッキス)である。古いけれども棄てがたい、その完成した美しい形は東洋人の二千年来の悲哀のさまざまな追憶に依てたとへがたない悲しい光沢をつけられてゐる」。ここには短歌の短歌たる原点的なイメージが語られており、短歌とはこのようだと直感的に納得させるひらめきがある。近代という文化的波乱の時代に語られた伝統詩のこのようなイメージは、さながら川の流れに沈んで光る白い小石のように振り返られてきたのではないか。
しかし、この美しい散文詩の姿をした短詩型論はつぎのようにも変奏されている。
「併し私はその完成された形の放つ深い悲哀を知ってゐる。実際完成されたものほどかなしいものはあるまい。四十過ぎた世帯くづしの仲居が時折わかい半玉のやうなデリケエトな目つきするほどさびしく見られるものはない。わかい人のこころはもつと複雑かぎりなき未成の音楽に憧れてゐる。マネにゆき、ドガにゆき、ゴオガンにゆき、アンドレエフにゆき、シユトラウス、ボオドレエル、ロオデンバツハの感覚と形式にゆく。かの小さな緑玉の古色は私がそれらの強烈な色彩の歓楽に疲れたとき、やるせない魂の余韻を時としてしんみりと指の間から通はすだけの事である。即かりそめの病に飲む一杯の古いシアンペンの味である」「古い小さい緑玉は水晶の函に入れて刺戟の鋭い洋酒やハシツシユの罎のうしろにそつと秘蔵して置くべきものだ。古い一絃琴は仏蘭西わたりのピアノの傍の薄青い陰影のなかにたてかけて、おほかたは静かに眺め入るべきものである。私は短歌をそんな風に考へてゐる。さうして真に愛してゐる」
ここには白秋が短歌を思いつつ抱くジレンマが切実に覗いているのを感じる。短歌に「四十過ぎた世帯くづしの仲居」の純情を見る白秋が、この形式を手中の玉のようにただただ愛したとは思えない。「短歌は一箇の小さい緑の古宝玉である」とは、単純な短歌への愛着の表白なのではなく、じつに苦いさまざまな物思いの凝縮なのではなかったか。二つ目のパラグラフは、最後に添えられた「真に愛してゐる」の一行がなければ、短歌は常にきらびやかな物の陰に置かれるべき古い器だと言っているのにすぎない。「刺戟の鋭い洋酒」「ハシツシユの罎」「仏蘭西わたりのピアノ」、どれもありったけ西洋の香りをたたえたきらびやかな小物たちが、短歌を「古い小さい緑玉」たらしめるのだ。これら舶来の、おそらく白秋も欲しかったであろう、異国の品々、また、当時燦然と輝いて衝撃をもたらした西洋の絵画や詩や小説や、それらのものに比較するとき、はっきりとこの詩形は貧しく、古く、小さく感じられたのではなかったか。白秋はそれを隠そうとはしていない。こうして描写された短歌の位置は、それだけで十分哀しいではないか。白秋が舶来の小物に例えているのは彼が本領とした自由詩だという見方もあろう。白秋自身の活動として、西洋が先進である詩を前面に、そして短歌の役割をその陰として考えていた、というふうに。しかしそうであればなおさら、ここには白秋の内面での書き分けの発想に、伝統的な韻文を西洋のきらめきとどのように対比対立させ居場所を見いだしていくのかという葛藤が滲む。
けふもまた泣かまほしさに街にいで泣かまほしさに街よりかへる
〈桐の花〉北原白秋
手にとれば桐の反射の薄青き新聞紙こそ泣かまほしけれ
指さきのあるかなきかの青き傷それにも夏は染みて光りぬ
〈桐の花〉の主調音であるこうしたセンチメンタリズムは、一種不可思議な感興を呼び起こしつつ、実のところ理解しがたい何かを含んでいる。二十代前半の恋愛の情緒が下敷きになっているとはいえ、いい年をした男がこれほど淡くよりどころのない感傷に言葉を任せるわけがわからない。感傷の韻律と言ってもいい震えを帯び、哀しむために哀しんでいるような言葉は、背景を捨象してその実なにが哀しいのかを決して明かさないのだ。この歌集に横溢する哀傷感は、どこか古色な趣味をまとって現代の私たちにあと一歩近づきがたい何かを感じさせる。このセンチメンタリズムは一体何だろう、この哀傷の根拠はどこにあるのだろうと。しかし、いまいちどその定型論を味わい直し、これらの歌の背後にある葛藤を視野に入れるとき、白秋の短歌には、圧倒的な勢いで開けてゆく時代のなかでの伝統的韻文そのものへの恋着と哀しみが韻律となって滲んでいるのではないかと気づかされる。白秋がこの「古宝玉」を奏でるとき、そこには、あらかじめ詩形が抱えた哀しみとそれゆえにそこからせりあがってくる韻律の力が音色として添っているのではないのだろうか。これらの歌には、青年の恋愛の哀傷に託された短歌という伝統的な韻文の近代における哀しみと、その哀しみに洗われることで生き返った韻文の新鮮な息吹とが滲んでいる。つまり、白秋は近代という、カルチャー〈クライシスの時代を生きつつ、一つの伝統論、文化論として短歌をまるごと抱えあげ、かなしんだのではなかったろうか、と思うのだ。彼のセンチメンタリズムは伝統的な韻文の近代における位置づけの葛藤から発しているのではないのだろうか。
もう少しこうした、時代の葛藤に立ち入ってみたい。白秋と歩みを同じくし、この時期の叙情性において近かったと思われる木下杢太郎を考えたい。杢太郎は白秋と新詩社時代から歩みをともにし、明治四十年代の南蛮趣味に先鞭を付け、白秋の〈邪宗門〉にも多大な影響を与えた。のちに〈木下杢太郎詩集〉に収められた未刊詩集〈緑金暮春調〉には明治四十一年に書かれた、「緑金暮春調」がある。この詩には白秋の〈桐の花〉の韻文論に先んじてその気分を伺わせるものが底に沈んでいる。
「ゆるやかに、薄暮のほの白き大水盤に/さららめく、きららめく、暮春の憂鬱よ。/その律やや濁り、緑金の水沫かをれば、/今日もまたいと重くうち湿り、空気淀みぬ。(中略)ああ暮春、この堂の錆びし扉は音なく鎖され、/西の空漸ゝ明かり、濃き空気おぼめきたるを、/ただひとり今もなほ、ゆるやかに、さはれ悲しく/さららめく、きららめく、ほの青き憂愁よ。」
この詩は全体として輪郭ははっきりしないが、どこかの古い寺院か教会を散策しながら自らに湧く「憂鬱(めらんこりあ)」を韻律にのせているふうに読める。「ほの白き大水盤」「この堂の錆びし扉」が古い豪壮な建物と中庭を想像させる。「西の空」をのぞむ東洋のどこか重々しく壮大な時間を閉じこめた伽藍。杢太郎はこの古い時間の沈んだ空間をさまよいながら、そこに幽閉されている憂愁を描く。この伽藍の風景に例えられたのは東洋とか日本とか地理上のはっきりとした空間ではない。思いの主を歴史の深い懐に閉じこめようとする象徴的な場であればいいのだろう。全体の響きには、自らがさまよい続ける韻文の古く輝かしく重い空気の淀んだ空間を重ねて想像できるのではないか。この当時の杢太郎について、啄木は日記の中で「太田君(杢太郎)の性格は、予と全く反対だと言ふことが出来ると思ふ。そして此、矛盾に満ちた、常に放たれむとして放たれかねてゐる人の、深い煩悶と苦痛と不安とは、予をして深い興味を覚えしめた」(明治四十一年十一月)と記すが、この詩にも、重い空間から放たれたい思いとそこに恋着してゆく心とは等量にせめぎあっているのが見える。
杢太郎自身はこの詩が書かれたころの運動体「パンの会」について、「概して曰ふと一種の欧羅巴主義(露西亜の文芸史の或時代に言われたやうな意味で)であつた。文学に於ける自由主義である。日本社会の封建時代的産物に対する反抗が之に加わつてゐたが、まだ社会問題がはつきり観点に現れてゐなかつた時代であるから、我々の思想の中心を形作つたものはゴオチェ、フロオベル等を伝わつて来た<芸術の為めの芸術>の思想であつた。この思想的潮流には本元でもエキゾチズムが統合した」と語る。明治のエリートとして中国、ヨーロッパにわたり、大正デモクラシーを通過した杢太郎の非常に恵まれた立場からは、社会の底辺で起こっている事は見えにくかったにちがいない。「封建時代的産物に対する反抗」と言いつつ何に抵抗すべきかは判然としていなかった恨みはある。この反抗も、杢太郎自身が述懐するように、社会的視点の欠如したものであったことは否めない。こうした脆さは、杢太郎のみならず、白秋も、晶子も抱えていよう。しかし、その反面、意識はより純粋に言葉の空間へ向けて、韻文の言葉と精神とをどのように新しい時代へ連れ出すのかというところへ凝縮していったともいえるだろう。帰国後の杢太郎が「近時東洋主義復興の聲を聞くがそれは回顧的あつてはならぬ。ざうりむしは無性的の増殖をもなすが、そのまゝにうち捨てゝ置けば遂には死滅してしまふ。他個體との接合が必要である。文明の繁栄にも他種文明との接合が必要である」と言うとき、それは、文明批評にとどまらず文学の徒としての直感も滲む。杢太郎は切実に直接に西洋に向き合い、西洋の精神との出会いであるキリシタン研究のなかに日本を模索したように、変化の中で日本のエッセンス見いだしてゆく。白秋の「古宝玉」の<発見>も、そうした流れの中で痛みを伴いながらなされたものであったと言えよう。
ところで、辻井喬が「日本文化はなぜ衰退したのか」(〈世界〉98/4)という文章の中で、「伝統とは日本の文学の場合は短歌・俳諧の、そこに見られる調べ、リズムと詠嘆と抒情の質、雪月花に代表されている美意識の統合としての表象の謂いなのだろうか」と問うている。これは、「私たちの文化はどこにあるのか」という特集の中での問いで、「木遣り、大相撲、道祖神、扇子、和服、天女、長野オリンピックの開会式でこれでもか、これでもかと展開された光景には、外国に媚びた〈ジャポニズム〉の匂いがした。(略)では、翻って、〈日本文化〉はいま、どこにあるのか、そう考えてみると、私たちの中に、共通の日本像が焦点を結ばないことに気づく」というリードを伴っている。確かに私たちはいま、誰にでも共有される日本像をもちにくい。ここに問われているような記号化した「ジャポニズム」を疑いはじめると、日本のイメージは宙に浮いてしまうのではなかろうか。辻井は昨今の<伝統>回帰への指向を「私達の伝統論が間違えるのは、オリエンタリズムと体制によって作られた〈伝統〉をそのままうけとってしまうところからはじまっているように思われる」と危惧し、「伝統文化には多様な性格と種類があり、その中からどのような伝統的美意識を取り出すかが問題の中枢にある事柄のように思われる」とする。たしかに時代によってとりあげられる<伝統>は少しづつ異なり、その意味付けや読み方さえも微妙に異なってきた。その時代に何が取り上げられたかで時代の性格を想像できるのも、<伝統>が一面ではないことを証すだろう。「伝統とは言うまでもなく、先行する時代の中で培われた文化の構造、運動法則、技術の総体」と辻井が語るのも納得できる。総体として、運動としての<伝統>の生態を忘れた記号化されたオリエンタリズムは、日本人にとってさえジャポニズムという異国情緒であり亡霊であろう。
疑うなら、白秋の「古宝玉」も、マダム・バタフライさながらのジャポニズムでないとはいいきれない。小さく、愛らしく、繊細で神秘な日本という異国の象徴として。しかし、長野オリンピックのジャポニズムと白秋や杢太郎の日本探しとが、決定的に違うのは、その痛みや生命感においてであろう。「古宝玉」という呼びかけそのものが白秋の内面のせめぎあう両極の欲求がもたらす緊張感、未知の予感を含んで震えていたはずだ。杢太郎の憂鬱(めらんこりあ)もまた日本の韻文への恋着とそこから歩みだして行きたい心とに裂かれた文化論の総体を背負っていたといっていい。杢太郎の論にしばしば現れるヨーッロパ礼賛が現在から見て異様に映るとしても、それが切実に日本の伝統と未来とを生き直す気迫に支えられていることは疑えない。辻井の論に加えるなら、<伝統>は発見し選ばれた歴史的なエッセンスと、もっとも個人的でありそれゆえに時代に深く染み着いた欲求とを統合し、あるいは対立させてどこか見知らぬ地点へ言葉を引きだそうとする<運動>そのものではないかということだ。
いま、<伝統>論議に危うさがあるとすれば、もう一つには方法としてかつて無いほど膨らんだ表現形式としての短歌が、大きな空白を抱えていることの反動として語られるときだ。一九九二年、〈現代詩手帖〉が「短詩形のゆくえ」を特集したとき、批評はそうした空白を語る言葉で埋まった。「気づいたら<私>はもはや根をもつことをやめ、宙に浮遊していた。新しい世代は<私>探しすらはじめからキャンセルし、<私>遊びに興じはじめた」「何ものも存在しないというのではない。あらゆるものがある。しかし、見ようとする時、そこにはただ空白のみがある」「しかしそれにしてもこの軽やかな表層性はなんだ」。時代的にはちょうどバブルの最盛期に向かっていったころだが、今もそれほど大きな差はないだろう。ただ、現在欲求として加わりつつあるのは、そうした短歌になにかしら中心や求心力を仮想しようとする動きだろう。定型はじつに柔軟に何でもとりこみ、膨張してきた。無限に拡散してゆく哀しみといってもいい。この中で失われたのは、<私>であると同時に<他者>でもあったのではないか。確かに近代は西欧というくっきりとした<他者>をともなってあらわれ、日本の伝統の何たるかを輪郭鮮やかに考えさせた特別な時代であったかもしれない。そうした鏡のないことも<伝統>論議を宙に浮かせているかも知れない。つまり中心がないこともよる空白なのではなく、外界がないことによる空白と考えた方がいいのではないか。外部や他者を感触できないまま<伝統>という中心を想定することにある危うさを感じるといってもいい。
私たちの言葉は、生き物として落ちついた濃密な居場所と解放された運動への希求という両方の相反する欲求を秘めている。その運動の震えを秘めていたのが〈桐の花〉の韻律だろう。しかし、短歌という詩形にまるで、ホームがあるような錯覚は言葉の運動を弱め創造性を弱らせてしまうのではないか。この短詩型に<伝統>というホームがあるわけではなく、またこの詩形が日本の文学のホームであるわけではないのではないか。ただ、どこかにホームを仮想したい心の集積を短歌が背負ってきたことは事実だろう。この短詩型をめぐっての議論には<伝統>と時代との葛藤がそのときどきによりエッセンシャルに刻みつけられてきたのだから。その闘い、<運動>自体をホームとよび、<伝統>とよぶなら、短歌はまさに蝸牛のようにホームを背負って移動し続けてきた生き物であると言えるかもしれない。