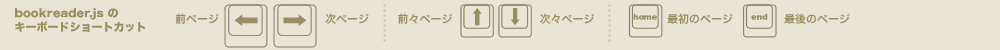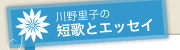馬場あき子論
— 寂寥に会ふごとく停車す —
「かりん」96・9
『暁すばる』書評
いつであったか能の果てた後の茶会の席で面と舞い手の素顔との関わりが話題になったことがあった。小面などの女面からはみ出した舞い手の頬の肉が興をそぐといった話が飛び交っていたが、そのとき馬場が、舞い手の素顔はぴったりと面に隠れてしまうより少しはみ出した方がいいのだと語ったことを記憶している。おそらくこうした議論にはさまざまな可能性がありえ、面打ちを手がける人などにとっては面そのものが可能な限り生きる使われかた、舞台というものがイメージされるだろう。また役者の風情への個々の好みなども反映しよう。しかしこの場面での馬場の言葉が能などに疎い私に印象的だったのは、それが何より馬場自身の言葉との関わりにも通う好みのように感じられたからだった。
人しらじ金輪際といふ際のさびしき汗をしづかに拭ふ
暁すばる天辺に淡く書きつげるこよなき時といふはさびしも
頬白はすばやきひかりこぼしたり声澄むは飢ゑに似てさびしけれ
白菜を一つ抱えてしぐれする師走の街を走るさびしも
呼び止めて秋大根を煮よといふ八百屋天坂の日照雨あかるし
金星の明るき宵のつづきゐて胸底に真珠眠れるごとし
馬場の第十四歌集である『暁すばる』は近年の馬場の歌の中でもひときわ人懐かしい素顔をのぞかせている。一首めは舞台の裏、あるいは面の内側での〈さびしき汗〉の告白であるが、そうした、馬場が表立ててこなかった場面でのもの思いは〈水洗トイレ音さやさやとひびききてかの客人も帰るにかあらん〉のように幅広い素材を取り込んでかしこに見られる。
前歌集『阿古父』では
地下道をきらきらと行く長脛彦うちほろぼしてやらむと思ふ
喉切れば正身あらはる父といふ明治の骨の怒りあらはる
のように、対象に迫りそこに現れてくるものを容赦なく見取ってゆく気迫が印象的であったが、ここでは等身大の日常を取り戻してゆく時間の静謐のなかから言葉が生まれている。都市風俗や死の床にある父親といった存在感濃い対象やそこへの強いメッセージ性は消え、肉親を失った哀しみの余韻とともに、ある安らかさも感じられる。こうして前歌集からの流れのうちに読むとき、急から緩へ、動から静へといったひと流れのリズムを感じることもできよう。「暁すばる」の章に収められた三首の〈さびし〉さはそれぞれにニュアンスを違え、質を違えながら、しかしそのどれもが重なって一人の生身の作者像へ滲んでゆくようだ。夜明けまで〈書きつげる〉ことや〈白菜を一つ抱えて〉〈師走の街を走る〉といったありそうな生活の場面に響きながら、〈さびし〉はそれぞれがどの寂しさにも還元することのできない微妙な味わいをたたえて身体性に近いものにつながってゆく。また四首目の〈天坂〉と〈日照雨〉の響きと淡い明るさとは〈秋大根を煮よ〉というような生活場面をつつんで軽い面白味を出している。五首目もあまやかな気分の歌だが、〈金星〉や〈真珠〉といった華やかな言葉選びながらどこか静まった物思いとなつかしさを感じさせる。この、ほぐれてゆく言葉から次第に現れてくるかのような〈生身〉の気配において『暁すばる』はこれまでの歌集と異なった顔をもっている。
『阿古父』までに顕著な世界については〈忘れねば空の夢ともいいおかん風のゆくえに萩は打ち伏す『桜花伝承』〉などの歌を引きながら米川千嘉子が「風景は情であり、情はすなわち風景であるような、柔らかに艶な景情融合の世界であり、それは和歌的な時間に刺さって、限定的な人称の世界をこえている」、「風景や景物を鍵に、多く和歌的な時間をかかえた馬場の世界では、さまざまなものが重層、交響する。その核にあるのが、情緒や場面、風景を含んだ和歌的、伝統的世界への返しの意識であり、それは和歌の世界の表現の骨であったものに他ならない。」(『短歌』平成六年十月号)と述べ、馬場の方法論を分析している。この歌集にも和歌的風景をモチーフにした歌は多いが、それが〈限定的人称の世界をこえて〉ゆくことよりはむしろ生身の身体をもったひとりの作者へと引き寄せられてゆくところに、従来の方法意識とは異なるものが感じられる。それゆえ提示された景物は〈和歌的時間〉の〈重層、交響〉性の力を離れて実物大の感触を持つ。実物大であることは一方では明らかに一首単位の世界を縮小しつつ、また一方では作者の影を濃くしてそこにあらたな味わいを生んでいるとも言える。試みに方法的にも馬場の歌を代表しうる一首とこの歌集の一首を比較してみるとその方向性の違いはより明らかになろう。
夜半さめてみれば夜半さえしらじらと桜散りおりとどまらざらん
『雪鬼華麗』
いづこならむ目ざむれば雨こまやかに寂寥に会ふごとく停車す
『暁すばる』
こうして並べてみるとこの二首は一対の、あるいは表と裏の言葉のように見えてくる。桜を鍵として和歌的文脈に流れる遥かな時間と応答するかのような一首目は、桜が呼び起こすさまざまな物語を引き連れながら、作者一人にとどまらない人間の生全体を貫く心として広がってゆく。そのめまいするような遥かな時間と空間をつなぎ止めているのが作者の影である。二首目は旅の乗り物に眠り、覚めたときの距離感をかみしめている歌であるが、停車した車中の感触、細かい雨のものさびしさなどは気配として作者の存在へと浸みてゆき、時代全体にこもる淡い疲れの感覚を引き寄せながら人生的な感慨を伝える。ここでは言葉は敏感に周囲の世界の気配を吸収しながら、広がってゆくよりはむしろ浸み込んで作者の影を濃くする方向に働いていよう。こうした方向性は、馬場自身の人生的な激しい時間の流れや、さらに時代全体がくぐりぬけたせわしなく高揚した時間ののちに訪れた等身大の自己を確認したい欲求と無関係ではあるまい。さまざまに展開されてきた言葉が自らの存在の実感や肉体性にひっそりと舞い戻り、自らをあらたに見いだすかのような歌が少なくないことは、また馬場が時代の空気を敏感に吸収していることを証してもいる。
老いて男は女体恋ふらし秋風にわが忘れをるわれなる女体
女なること忘れをりしが夏たけて鯉魚たり夢に濃きやみを泳く
茂吉はもさるとき鰻食ひにけむかかる拙き恋堪ふるとき
とろろめし好みし男ともだちの大き臼歯を思ふ春の夜
ふと思へばわれ情あつく愛淡きこと折ふしのあやまちなりや
女性という性を伴った老いはテーマとしてまだまだ未開拓だ。一首目。男の性が老いてなお肉体性と濃い関わりを持つのに対し、性そのものからほどかれてゆくかのような女の老いの発見は軽やかでありまたせつない。そうしたあらたな気づきによって見いだされる濃い伏流のような性が夢を語ることによって告白されているのが二首目であろう。ここには老いを得てむしろ自在な身体が備わったかのような始まりの感覚もある。そして気がついて見れば茂吉が鰻を好んだことも性そのもののなまめかしさと哀しさとして引き寄せられる。記憶の男友達の臼歯、つまり奥歯を想像するというのも時を隔てて思うゆえの自在さと、しかもかなり大胆なエロスを含んでいる。五首目はむしろ馬場の日常に取材した、あえて愛や性などと関わりない歌であるかもしれない。だが、こうした悔いそのものに滲む思いの濃さが日常の感慨を越えて、思うことそのものに肉感を与えている。こうした〈生身〉の再発見には馬場が女にとっての老いという物語に積極的であり自覚的である姿勢が伺える。老いをテーマにしながらなまめかしく生命力にあふれているのは馬場がそこに新たな女の時間を見ようとしているからであるが、また、どこかその文体から自然に滲み出てくるもののようにも感じられる。馬場には常に、ほとんど無意識に対象からより生命感つながるものを引きだそうとする姿勢があり、それが芯の強さや自在さとなって幅広い素材を自らのものにすることを可能にしている。
松田修は『世捨て奇譚』に寄せた解説のなかで「その混乱〈絶望〉暴力等々がもっとも極まった暗黒の季節」を描く馬場の筆致についてこう述べている。「そこには冷静で節度ある距離が置かれている。どれだけ深い共感があっても、それは、明快な論理・論証によって解晶され、再構成される。おどろおどろしく腥い事件たちも、あざやかな整理とゆき届いた解釈、強靱な文章力にからめとられてしまう。〈この一筋の界線こそが、馬場あき子と馬場あき子の『裡なる鬼』とを区分けし、後者を対象化することによって、作家的自立を可能にしているのである〉もし馬場あき子の『裡なる鬼』が、ストレートにペンを執るとすれば、一冊ごとに自死自刎をもたらすのではないか。生きて見て書き続けるためには、節度としての距離が、必要ではなかったのか。」と述べる。ここには馬場の散文についての重要な特徴が指摘されているが、これは歌についても重なる部分をかなり含んでいる。歴史的な重い負の情緒を多く自らの猟場としながら、馬場にとってもうひとつ重要であったのは、そうした劇的世界から立ち戻る力、それらを制御し明るみにしつつ日常の時間に繋げてゆく生命力であったと言えよう。しかしまたその文体が持つ力強さや明るさ、人懐かしさは、限りなく思いを寄せながらどこかで自らのために踵を返し生の穂をついでゆくことを選ぶせつなさと、またそれゆえの哀しみを引き受けることを底流にしてもいる。馬場の文体が男性的な張りと闊達なリズムをもち、その主題が思想性に支えられていることは多くの読み手によって指摘されるとうりである。また複眼的な人間把握やその幅広さと自在さは、複数の人間によって綾なされる精神史にひとつの人格を与えるようでもある。さらに、先に米川の指摘にあった〈和歌的な時間〉との応答によって開かれる世界は艶にやさしく、時空を隔てて共鳴する哀しみを抱える。だが、そうしたいわば公な精神史に参入し応答することと個の時間や存在にそうした言葉を引き取ってみせること、その二つの相反する欲求を同時にかなえることはそれほど簡単なことではない。そこには開かれた外界によく感応し物によくつく心と、同時に、冷静な理性と孤独との両方が備わっていなければならない。松田が述べる〈馬場あき子と馬場あき子の『裡なる鬼』〉を区分けする〈一筋の界線〉とは同時にそれを結ぶ線でもある。それはあるいはそれはねばり強く世界を肯定し受け入れてゆく生命力に支えられた文体そのものであるかもしれないと思う。
鬼を為るこころといふはうつしけもなしまつさらな夜の闇は来て
秋田地方のなまはげを見物に行っての作だが、張った韻律が祭りの高揚感を伝え、〈うつしけもな〉い乱舞にはある種の爽やかさが感じられる。この鬼は厚みある生活の力強い穏やかさの中に立って、鬼となり得た開放感を伝えている。この歌を含む巻頭の一連は、テーマも韻律もこれまでの馬場の流れの中に順当にあって特に目新しさを感じさせるものではない。しかし、ここで少し立ち止まってみたいのは〈鬼を為る〉という言葉である。これはこの歌を含む一連のタイトルともなっており、漠然と了解される鬼を演ずるという無機的な動詞にとどまらない奥行きをもった言葉として注意深く選ばれているように見える。背景としてここでは『風姿花伝』を考えるのが一番自然なのだろう。「鬼ばかりをよくせん者は、鬼の面白き所をも知るまじき」「餘の風體を殘さずして、幽玄至極の上手と人の思ひ慣れたる所に、思ひの外に鬼をすれば、珍しく見ゆるる所、これ、花なり。」は、ここでの〈鬼をすれば〉に気分として最もかなっているように思う。舞うのでもなく演ずるのでもなく、そのものになってしまうのでもない〈為る〉鬼は、地味な生活を常とする者の〈思ひの外〉の姿であるからこそ興深く、ひとときの正体ない陶酔を呼ぶ〈思ひの外〉の〈花〉としてあると言えよう。同時にこの言葉は馬場がこうした世界に身を置き言葉をもって立ち返る時の気迫に似てもいるのではないか。馬場がこの秋田や長年通い続けている山形の黒川を始め各地の芸能を旅の中に追い続けるのは、日常のなかに非日常を取り込み結ぶ〈為る〉ことのダイナミズムに言葉の生きる場を感じているからであろう。それは非日常を取り込みつつ日常を生き次ぐ人々の生の全体性への信頼や憧れを滲ませ思想となって、一つの世界となっている。しかし一方ではそうした世界において馬場は常に見る側に徹するほかないのであり、まさに言葉そのものとなって呼吸を合わせるような文体の力によってこそ馬場と地方の祭事や人間模様が結ばれる。〈為る〉はそれゆえ馬場自身にとっての主体のありように繋がる言葉であり、象徴的に劇的場面と人間の生身とを橋渡しする言葉としてことに大切に扱われている。
〈鬼を為る〉者は同時に鬼の面を取った素顔をもっていなければならない。〈為る〉ことのダイナミズムはむしろその生身のありかによって支えられるからだ。『暁すばる』はその意味で〈思ひの外の〉の生身をさりげなく滲ませながら、馬場の歌の流れの中で言葉の厚みとして働いている歌集と言えるだろう。