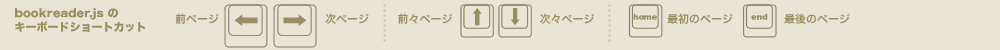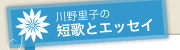安永蕗子第二歌集『草炎』
— 志の華 —
「短歌」02.3
安永蕗子の歌を考える上で第二歌集『草炎』は大切な要素を含んでいる。第一にこの歌集では後の安永作品の特徴である抽象度の高い引き締まった精神世界の輪郭が示され、第一歌集『魚愁』にみられた生活の具体や影が消されてゆく。ある意味ではスタイルや方法に対する覚悟の集としての意味を持つと言えよう。
麦秋の村すぎしかばほのかなる火の匂ひする旅のはじめに
露おきて花野のごときあかつきにあはれ闘ふ意志ゆゑに覚む
巻頭に置かれた二首である。「村」が安永とどのような関わりをもつのか、そうした関係を問う問いを一切遠ざけながら村は描かれる。世界の全てが行きずりであり、しかしそれゆえにこのうえもなく大切であるような出会いが記されているといってもいい。村にとってのよそ者であるのみでなく、この世のよそ者になることによって感受できる何か、それが「火の匂ひ」なのである。この巻頭歌によって、安永はこの世の一切に対して自らは旅人であると宣言する。そして二首目、何のための闘志なのかここでもその具体は消され、暁の美しい光の広がりが示唆される。草木ではない自らは闘志によって自らの輪郭を磨き、暁の光と一線を分かつのである。これは周囲を消し去るという消去法によって純度を高められた闘志であり、読み終えた者はそれら全てが美しさへと奉仕していることに気づかされる。この美への傾倒が以後の安永作品を方向付けたと言えよう。
このように現実から身を引き抜き、より抽象度の高い表現へと飛躍しようとする歌からは、草木の一本一本、蕪や、家禽や砂浜や山道やそのほかさまざまなものが一対一の対話の場に引き出されてゆく。それは、あきらかに生活の脈絡とは別の場に据えられたものたちであり、作者の濃厚な思惟を支える受け止める器として現れる。
もろともに草の峠をわたるとぞはかなけれども凌駕のひとつ
寂しみて籠の鳥見れば鳥もまた自が悪相のなかに眼つむる
「もろともに」とは何と共になのか、何を供に、そして友として峠を越えようと言うのか、言葉は空中を差したままである。しかし、この歌を読む者は峠を越えようとする風の音を聞き、目に見えぬ者を確かな供として生きようとする志のようなものを感じ取る。孤独への覚悟、といえば分かりやすいが、しかしそれ以上に感じるのは、あらゆる者が意志を持って生きていることの手触りのようなものである。そして自らもその意志によって自らを名乗る。二首めの鳥の瞑目のさまも孤独と同時に意志の深さ、強さを感じさせる。小鳥の顔のよく見ればハ虫類によく似た目元は、鳥自身が変えることのできない運命としてその身に備わっている。その運命の中に身を沈めるときに鳥は深い意志の表情を見せるのである。
安永の歌にはどこかこの運命との対話といった主題が通っており、あらゆる事物はその対話の場に引き出されて輪郭を露わにしている。運命が変えることの出来ないものならば、この対話によって可能なのは自らの意志を示し、闘志を輪郭として立つことである。どの歌もきりりとした韻律とシャープに切り取られた抽象性を持つのは、志を志として立たせるためではなかろうか。緩みや甘えの入る余地のないところへ言葉を磨き上げ、追い込んでゆくこと、それを美意識が底深く支えるとき安永の歌は独自の表情を見せる。これは一種のミニマリズムの試みと言えるかも知れない。この歌集で安永はこのミニマリズムの試みを自らの方法として抱え、確立したように思われる。
母の遺骨もちて旅ゆくかすかなる母の韻きは風にまぎれず
おそらくこの歌が安永と現実との別れの最後の歌となったのではないだろうか。はかない遺骨となった母は、全てのものが風に流れ抽象に退いてゆくなかで、風に紛れない韻きとなったという。もしこれが音楽ならば通奏低音のようなものかもしれない。すなわち、この後入ってくる音全てと響きあい、全ての音を和音に変化させる音である。この母の遺骨のような何かを安永は常に抱えている。それは愛の名残のようなものであり、愛の口惜しさであり、余韻でもあって、安永の美の根幹を支えている何かであるように思う。
いつからか、述志という言葉が消えてしまった。この歌集以後安永が執拗に追い求める言葉にはこの、消えてしまったはずの志という言葉が相応しく思われる。そして安永の述志こそは愛の名残の華やかさを纏って孤独なのだ。